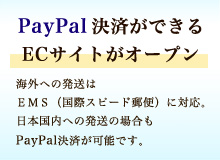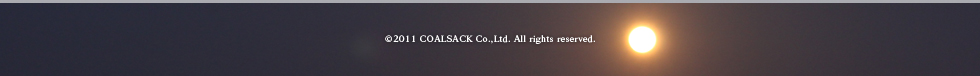<詩作品>
むかしあった練兵場で
ミーン ミンミン
兵隊さんが松の木に登って
鳴きわめいている
―声が小さい
鞭を持った奴がどなる
十人ばかりが練習をしている
K君が指をさして笑うと
吊り上がった目がこちらに向いた
ぼくは逃げた つんのめった
驚きと怒りの血を土が吸った
師団道で小旗を振って見送った
鉄砲をかつぎ 重い背嚢でうつむき加減
お国に尽くす兵隊さん
ぼくらの英雄
その兵隊さんがあんな事をされるとは
K君が来て言う
山の女学校で首吊りをした兵隊がいたんだ
中学校に教練という軍事訓練の時間があった
日射しが皮膚を刺す日
整列のときに汗をぬぐうと
―汗をふいた奴 一歩前へ
配属将校の威圧する声
ぼくと三人が出る
罰で休憩時間も立たされた
―汗をふいた者はぎょうさんおった
―今日先公の虫の居所が悪かったんじゃ
唇をかんで耐えた
鈍い音をたてて一人が倒れる
担任が駆けつけた
助かった K君が注進したのだ
それ以来教練には
―前へ進め(後ろに行ったるわ)
―捧げ銃(鉄砲をおろしてやる)
と反発
三年生になり勤労動員で工場に行かされて
ほっとした
戦局は悪く日本が危ういというのに
阿修羅は多くあった事を粉砕し
時間を無色にした
すべての思いを絶ち
心を鎮めて木立を歩いた
むかし練兵場だった公園に
わくら葉が降っている
裏になり表になって重なる命
片隅の記念碑にも積もる
明治四十一年岡山十七師団
わずかに読み取れる苔むした石
いじめられっ子の声がする
戸板の人は
「ピカにやられたんか」
近所の親爺の声
「広島からよう連れて来たのう」
生きているのか死んでいるのか
戸板にのせられ
わずかに土色の顔を覗かせ
頭を垂れた一行が北に行く
瓦落多の街を縫いながら
火傷の足を押え
広島のニュースを聞いた
―新型爆弾投下
―一瞬の光で死傷者多数出た模様
タブロイド型の新聞は多くを語らない
さらに大本営発表もない
「一発で広島は全滅したで」
「四十万は死んだと言うで」
噂は影となってしんしん広がる
檻褸をかぶせた戸板の人
日本はもう駄目だ
まだ本土決戦だと
竹槍の訓練をしていたが
ヒメムカシヨモギが生えた
もう生物はだめだと言われる
ヒロシマの赫土に
敗戦後三年広島の街に行った
焼けトタンの屋根のバラックが点在する
どのうちもコスモスの花が
土をピンクに染めて
花の首がゆれる
バラックに人がいる
戸板にのった婆ちゃんが
花を見ている
クジラの独り言
小鳥の声に目をさました
なにかを訴えている
窓を開けて耳をそばだてると
カザルスのメロディーを残して
舞い上がった
言葉でさえ
なかなか心の谺を伝えてくれない
中国の若者の排日デモ
いまの日本人にはよく伝わらない
郵政民営化の大事な法案
与党の議員でさえ分からない
前夜仕込んだ知識を
机をたたいて教えたが子供達は生あくび
三十年連れそった妻でも
遺品の日記に
主人には私の言葉が通じませんと
七十年来使って来た文言は
朦朧として形を成さず
指を開いて空をつかむ
あげつらうように
自分の詩の連なりが
巻き上がりながら消えていく
アメリカ海軍の潜水艦の記録には
ヒゲクジラが
十二年ただ一人で遊泳していると言う
これまで聞いた事のない
声を発しながら
*パブロ・カザルス「鳥の歌」
霞んだ空から
便りが届いた
「梅の花が咲きました ちえ」
住所がなく 写真が一葉
妻の名はちえこ
心覚えがない
封筒を返す
ほのかな香り
スナックのママに
プレゼントをした小枝
蕾がほころびたか
「えっ そんな便りがねえ」
壺の位置をかえながら
「きっと奥さんからの贈り物よ」
亡くなった妻の事など
知らないはずなのに
ちえ という文字
くずしていて
さえとも たえとも読める
妻の友達だろうか
遺品をさがすと
カビのにおいが広がった
ノートを繰るのをやめる
二十年もたっている
妻からだろうか
花をさした備前焼の壺
生前よく撫でていた
一度だけ夢に出てきた
彼女が畑に植えた梅が
強く香った日に
まさか
末娘の顔が浮かぶ
中学三年のときに妻は亡くなった
あと五年生きたい
娘は妻のつぶやきを聞いている
嫁入りに遺影を抱いていた
電話口に急ぐ
電話機を上げるのをやめて
庭に出た
霞んだ空から花びらが下りてくる